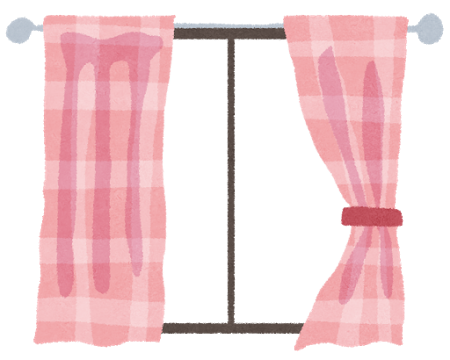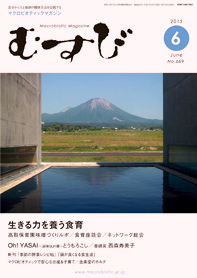(その1より続く) オオバコ・タンポポ・桑・ギシギシ…おなじみのものもあれば、名前は知っていても、見たことがない(見ても分からない)もの、初めて聞くもの…次々と出会います。途中で別のハイキンググループとすれ違い、「こんにちは」と挨拶を交わします。この日のコースは、「山野辺の道」の一部なので、私たちも一見ハイキンググループなのですが、 なぜか下ばかり見て歩いている、不思議な人たちだったことでしょう(笑)
なぜか下ばかり見て歩いている、不思議な人たちだったことでしょう(笑)
天理市トレイルセンター(左写真)で少し早めの昼食。各自お弁当を広げて食べ始めると、先生が持って来てくださった自作の「くちなしときゅうりの酢の物」「びわ味噌」「桑の実ジャム」を分けてくださいます。これがどれも美味しい!あのくちなしの花が(どなたか歌い出してませんか?笑)酢の物になるなんて!早速やってみよ~(^^)
 昼食後、再び歩き出しました。空はだんだん泣きそうな気配、時々立ち止まって、先生の説明を聞きながら、進んで行きます。やがて雨が降り出し、ザーザーとかなり激しくなって来ました。そうなるともう摘み菜どころではなく、纏向(まきむく)駅まで、ただひたすら歩きました。最後の1時間ほどは雨に降られましたが、とても楽しい摘み菜体験でした。こんな草が…と思うものが、実は食べられることに驚き!とても勉強になり、本当に満足しました。毎月1回の講座というのも参加しやすいペースなので、これからも是非続けていきたいと思います。
昼食後、再び歩き出しました。空はだんだん泣きそうな気配、時々立ち止まって、先生の説明を聞きながら、進んで行きます。やがて雨が降り出し、ザーザーとかなり激しくなって来ました。そうなるともう摘み菜どころではなく、纏向(まきむく)駅まで、ただひたすら歩きました。最後の1時間ほどは雨に降られましたが、とても楽しい摘み菜体験でした。こんな草が…と思うものが、実は食べられることに驚き!とても勉強になり、本当に満足しました。毎月1回の講座というのも参加しやすいペースなので、これからも是非続けていきたいと思います。
下写真、左から順に「くちなしときゅうりの酢の物」、「桑の実ジャム」、「イノコズチの吸い物」です(各々クリックで拡大)。左の二つは先生が持参されたもの、右の吸い物は私の自作です(^^) by ichi